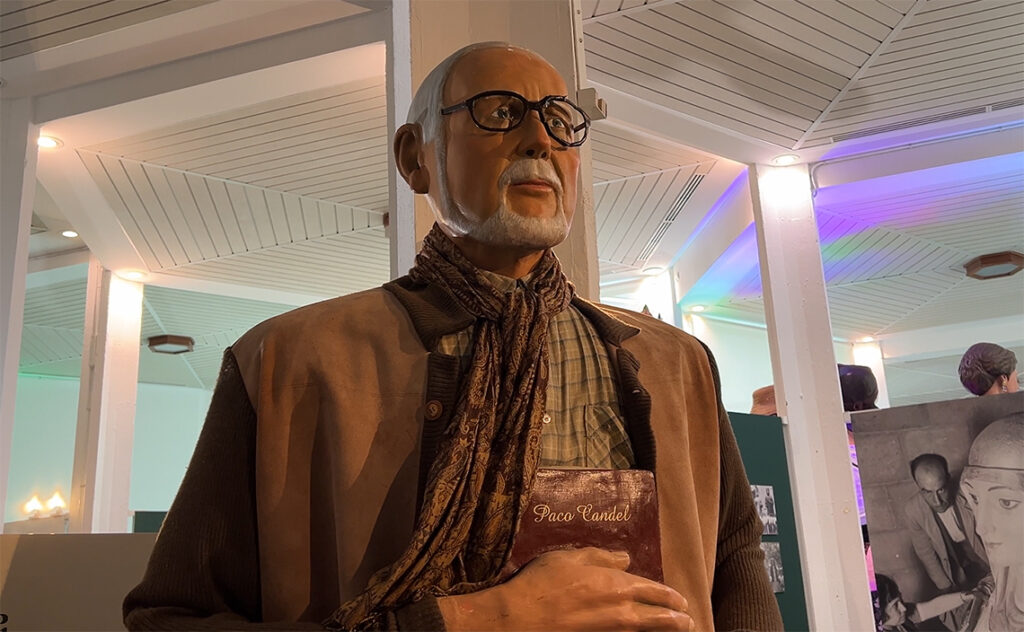見た目以上に「迷い」を抱える博物館Museu Etnològic de Barcelona
バルセロナの南西部、モンジュイック山の中腹に立つMuseu Etnològic de Barcelona。世界中から集められた約70000点以上の民族資料を収蔵する、スペイン屈指の民族学博物館である。ところが、この博物館は自らが何であるかについて、迷いながら歩んでいる。その迷走の軌跡を辿ると、近代のヨーロッパが世界とどう向き合ってきたのか、そして今それがどう問い直されているのかが見えてくる。
100年近い歴史の中で幾度も名前を変え、何度も統合し、その度に展示内容を修正してきたこの博物館。なぜこんなことが起きているのか。それは単なる組織の都合ではなく、スペインという国家がその文明史の中で何度も自らのアイデンティティを問い直してきたことの表れなのだ。

※公式サイトも迷走中

何度も名前を変えた百年の歴史
この物語は1920年代、スペイン文化人の志から始まる。当時の知識人たちが夢見たのは「伝統社会の情報センター」だった。工業化によって失われていく伝統的な暮らしの形を記録し、保存し、後世に伝える。そうした使命感から、民族学的な収集活動が開始された。
1942年、カタルーニャの民俗工芸に特化した Museu d’Indústries i Arts Populars が誕生した。この時点では博物館の見立ては比較的シンプルだった。農村部で使われていた民族衣装、台所用具、工芸品といった実用品を、地元の文化を示すものとして展示するという、地に足のついた試みだった。

万博を境に変わり始めた博物館の役割
ところが1949年、時代が変わると博物館も変わった。当時のバルセロナ万博のパビリオン跡地に新たに Museu Etnològic i Colonial(民族学・植民地博物館)が設立される。ここで大きな転換が起きた。スペイン帝国がかつて世界中に持っていた植民地や支配圏から、あらゆる民族資料が集められ始めたのだ。
この転換は単なる収蔵品の拡大ではなく、博物館自体の志の根本的な変化を意味していた。「民族学」と「植民地」を名に冠するこの施設は、スペインのグローバルな視点を世界に示す、ナショナルなプレステージの象徴となっていったのだ。かつて遠い異国の珍しい品々を見ることが最大の娯楽であり教育であった時代において、世界規模での収集は国家の威信そのものであった。

表面的には多文化を伝える空間
1999年の統合によって、約70000点を超える収蔵品を持つ大規模な民族博物館へと生まれ変わる。アフリカ、アジア、オセアニア、アメリカの資料が網羅的に並べられるようになった。一見すると、「世界を知る場所」に見える。だがその本質は根本的に異なっていた。

中立ではなかった「収集」という行為
Museu Etnològic de Barcelona(MuEC)の展示室を歩くと、アフリカの木彫り、アジアの民族衣装、オセアニアの祭祀道具など、圧倒的な量の資料が並んでいる。しかし、これらの展示品の多くには共通する欠落がある。それは「誰が、いつ、どこで、どのような文脈で使用したのか」という情報の不透明さである。
多くの展示物は「各国の実用品」という名目で並べられているが、その実態は、ヨーロッパ人がその文化を象徴すると見なしたものを、恣意的に収集・編集したものに過ぎない。現地の人々にとって日常の道具であったものが、コレクターの手に渡った瞬間に「アフリカを代表する呪術の道具」や「アジアの工芸品」というラベルを貼られ、剥製のように固定されてしまったのだ。

「劣った存在」と見なした人々の分類方法
ここにあるのは「世界を知るための窓」ではない。むしろ、当時のスペイン人が、自分たちより劣っている、あるいは自分たちとは決定的に異なると見なした人々を、どのようにカテゴリー分けして管理しようとしたかという、ヨーロッパ側の偏ったフィルターを映し出す鏡である。それを収集した側の権力的な視線が、展示品そのものが持つ本来の生命力よりも強く漂っている。
例えば、スペインがかつて統治していた赤道ギニアやモロッコから持ち込まれた品々には、単なる学術的調査の成果としてだけでなく、支配圏からの「収集」という側面が色濃く反映されている。それらは支配の正当性を証明するための証拠品として集められた歴史がある。現在の博物館は、それらを現代的な展示手法で包み隠そうとしているが、根底にある「他者を切り取る」という収集の構造は、展示の節々に露呈している。
なぜこのような状況が生まれたのか。それは当時の収集者たちが、文物の使用文脈よりも、「珍奇さ」や「美的価値」に目を向けていたからだ。その結果、資料は元の文脈から切り離され、ヨーロッパの美学的フレームの中に再配置されてしまったのである。

迷走の現在地——何を言いたいのかわからない展示へ
そして2017年。Museu de Cultures del Món との統合によって、博物館はもう一度、自らの方向性を問い直すことになる。新しい名称 Museu Etnològic i de Cultures del Món(MuEC)の下、2つの会場で運営されることになったこの機関は、明らかに異なる志向性を持ち始めていた。

植民地主義の痕跡が残る展示
なぜこのような転換が必要だったのか。価値観が多様化した現代において、単に資料を並べるだけでは「略奪の歴史」を再生産しているという批判を免れないからだ。しかし同時に、収集した膨大な資料を捨てることもできず、かといってかつての植民地主義的な説明をそのまま続けることもできない。その板挟みの中で、MuECの展示は「人類学的な視点」という抽象的な言葉に逃げ込み、結果として「何を言いたいのかわからない」という迷走状態に陥っている。
これは決して批判ではない。むしろこの迷走そのものが、近代ヨーロッパの知のあり方が、現在どのような困難に直面しているかを示す貴重な指標なのである。博物館は自らが何であるかを定義することができないまま、来館者に向き合わざるを得ない状況に置かれている。
バルセロナを訪れた観光客の多くは、この博物館を「スペインの民族工芸をまとめた場所」や「世界の民族資料が見られるエキゾチックなスポット」くらいに考えるかもしれない。だが、その内部では静かに、深刻な自己問い直しが続いている。



もやもやを抱えたまま観察する
Museu Etnològic de Barcelonaは完成度の高い博物館とは言い難い。だがその迷走ぶり自体が、近代ヨーロッパが世界をどう切り取ってきたかを映し出している。来館者が注目すべきは、各展示品がいかに丁寧に説明されているかではなく、その説明の隙間に何が隠されているのか、あるいは説明できていないのかという点である。違和感を覚えながら展示を見る体験こそが、この博物館の最大の価値なのかもしれない。