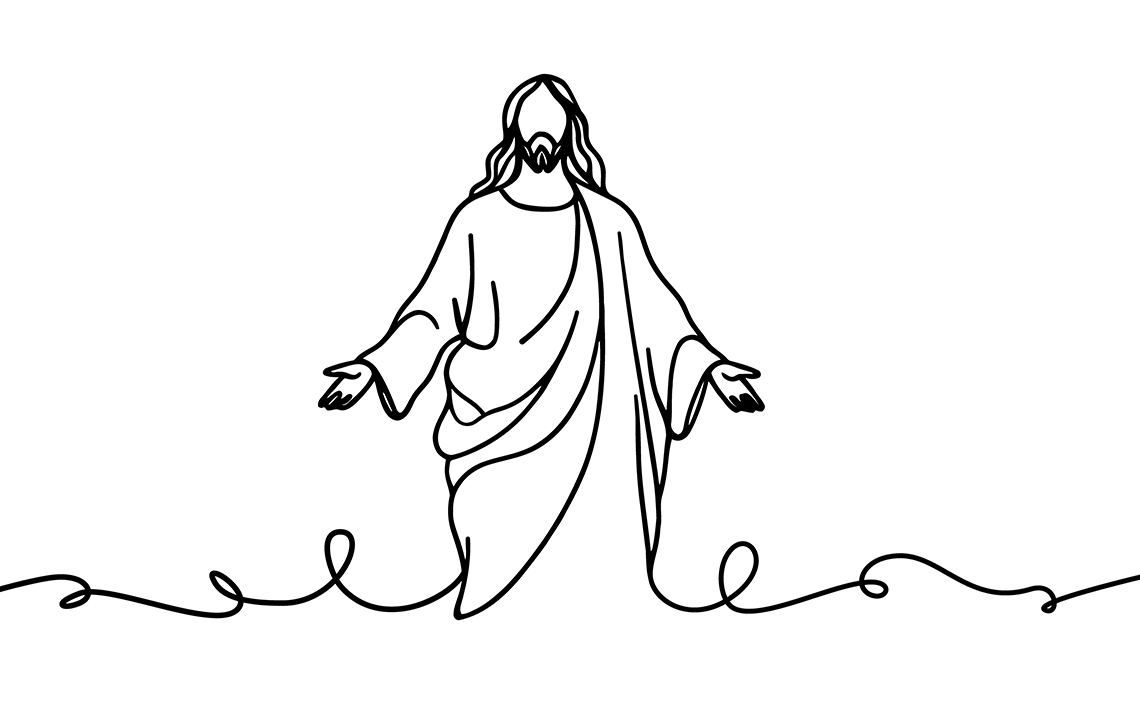スペインで宗教を抜きに歴史を語れない理由
スペインという国を思い浮かべると、サッカーやフラメンコ、美味しい料理などが頭に浮かぶかもしれません。でも実は、スペインの歴史を知るためには、宗教の話を抜きにすることができません。なぜなら、スペインでは2000年以上もの長い間、いろいろな宗教を信じる人たちが暮らし、時には仲良く、時には争いながら、今の国の形を作ってきたからです。
古代ローマ時代とキリスト教の始まり
今から約2000年前、スペインがある場所は「ヒスパニア」と呼ばれていて、ローマ帝国という大きな国の一部でした。ローマ帝国の人々は、たくさんの神様を信じていました。雷の神様、海の神様、戦いの神様など、何か困ったことがあると、それぞれの神様にお願いをしていたのです。
ところが、紀元後の時代になると、キリスト教という新しい宗教が生まれました。キリスト教は、イエス・キリストという人の教えを信じる宗教です。イエスは「神様は1人だけで、すべての人を愛している」と教えました。この考え方は、当時としてはとても新しいものでした。
最初、ローマ帝国はキリスト教を認めませんでした。キリスト教を信じる人たちは、隠れて集まって祈りをささげなければなりませんでした。見つかると罰を受けることもありました。でも、キリスト教を信じる人はどんどん増えていきました。
そして313年、ローマ帝国の皇帝コンスタンティヌスが、キリスト教を認める決断をしました。これによって、ヒスパニアでもキリスト教が広まっていくことになります。教会が建てられ、多くの人がキリスト教徒になっていきました。
面白いことに、スペインには今でも、この時代に作られた教会の跡が残っています。地下に隠れて祈りをささげた場所や、初期のキリスト教徒が描いた絵なども見つかっています。

イスラム教と三宗教共存の時代
711年、スペインの歴史に大きな変化が起こりました。北アフリカから、イスラム教を信じるムーア人という人たちがやってきたのです。イスラム教は、ムハンマドという人が伝えた宗教で、唯一の神アッラーを信じます。
ムーア人たちは、あっという間にスペインの大部分を支配しました。彼らはこの土地を「アル・アンダルス」と呼びました。でも驚くべきことに、ムーア人たちは、キリスト教徒やユダヤ教徒がそのまま自分の宗教を信じることを許したのです。
この時代のスペイン、特にコルドバという町は、世界でも珍しい場所でした。イスラム教のモスク、キリスト教の教会、ユダヤ教のシナゴーグが同じ町に並んで建っていたのです。イスラム教徒の学者とキリスト教徒の学者が一緒に本を読んで議論したり、ユダヤ教徒の医者がイスラム教徒の王様を治療したりしていました。
この時代には、「翻訳学派」と呼ばれる人々がいました。彼らは、アラビア語で書かれた古代ギリシャの本をラテン語に翻訳しました。このおかげで、ヨーロッパの他の地域では失われていた知識が、スペインを通じて再びヨーロッパ全体に広まっていったのです。
コルドバの大モスクは、今でもスペインで最も美しい建物の1つとして知られています。何百本もの柱が並び、赤と白の馬蹄形のアーチが特徴的です。面白いのは、このモスクの一部が、もともとキリスト教の教会だったことです。そして後に、モスクの中に再びキリスト教の大聖堂が建てられました。1つの建物の中に、2つの宗教の建築が混ざっているのです。
ただし、この時代がずっと平和だったわけではありません。時には宗教の違いから争いが起こることもありました。それでも、今から考えると、3つの宗教が同じ場所で何百年も共に暮らしていたことは、とても珍しいことでした。

レコンキスタと宗教統一の道
スペインの北部には、ムーア人に征服されなかった小さなキリスト教の王国がいくつか残っていました。これらの王国は、少しずつ南に向かって領土を広げていきました。この動きを「レコンキスタ」と言います。レコンキスタとは「再征服」という意味で、キリスト教徒がスペインを取り戻す運動のことです。
レコンキスタは約800年という、とても長い時間をかけて進みました。途中で多くの戦いがありました。でも面白いことに、この長い期間の間、キリスト教徒とイスラム教徒は戦いだけをしていたわけではありません。時には同盟を結んだり、結婚をしたり、一緒に商売をしたりもしていました。
1469年、スペインの歴史で重要な出来事がありました。カスティーリャ王国のイサベル王女とアラゴン王国のフェルナンド王子が結婚したのです。この2人の結婚によって、スペインは1つの大きな国になる道を歩み始めました。
イサベル女王とフェルナンド王は、熱心なカトリック教徒でした。カトリックとは、キリスト教の中でも、ローマ教皇をリーダーとする教派のことです。2人は「カトリック両王」と呼ばれ、スペイン全体をカトリックの国にしようと考えました。
1492年、ついにレコンキスタが完了しました。グラナダという町にあった最後のイスラム王国が降伏したのです。グラナダのアルハンブラ宮殿は、イスラム建築の最高傑作として今も多くの観光客が訪れています。宮殿の壁には、美しい模様や文字が彫られています。水が流れる中庭や、細かい装飾が施された天井は、イスラム文化の素晴らしさを今に伝えています。
でも、この年は喜ばしいことばかりではありませんでした。同じ1492年に、イサベル女王とフェルナンド王は、ユダヤ教徒をスペインから追い出す命令を出したのです。ユダヤ教徒は「カトリックに改宗するか、国を出るか」の選択を迫られました。多くのユダヤ教徒の家族が、長年住んでいた家を離れ、他の国へと旅立ちました。
追い出されたユダヤ教徒の中には、セファルディムと呼ばれる人々がいます。彼らはスペインを離れた後も、何百年もの間、スペイン語の古い形を話し続けました。その言葉は「ラディーノ語」と呼ばれ、今でもトルコやイスラエルなどで話されています。彼らの歌や物語には、故郷スペインへの思いが込められています。

異端審問が人びとに植え付けた恐怖
1478年、イサベル女王とフェルナンド王は「スペイン異端審問」という制度を始めました。異端審問とは、本当にカトリックを信じているかどうかを調べる制度です。
特に疑われたのは「コンベルソ」と呼ばれる人々でした。コンベルソとは、ユダヤ教やイスラム教から改宗してカトリック教徒になった人たちのことです。異端審問官たちは「コンベルソの中には、表向きはカトリック教徒のふりをしているだけで、隠れて昔の宗教を信じている人がいる」と考えました。
異端審問の方法は、今の私たちから見ると、とても恐ろしいものでした。誰かに密告されただけで疑われることがあり、裁判では拷問が使われることもありました。有罪になった人は、財産を没収されたり、火あぶりの刑に処されたりしました。
トマス・デ・トルケマダという人は、初代の異端審問長官として有名です。彼は厳しい取り調べで知られ、多くの人を処刑しました。ある歴史家の計算によると、異端審問が最も厳しかった時期には、年に何百人もの人が処刑されたと言われています。
異端審問は、人々の心に恐怖を植え付けました。隣人が隣人を疑い、家族の中でさえも信頼できなくなる雰囲気が生まれました。金曜日の夜にロウソクを灯すだけで「ユダヤ教の安息日を祝っている」と疑われたり、豚肉を食べないことが「イスラム教徒の証拠だ」とされたりしました。
でも興味深いことに、異端審問は単純に宗教だけの問題ではありませんでした。時には政治的な理由や、財産目当てで人々が告発されることもありました。お金持ちのコンベルソが告発されると、その財産は王室のものになったからです。
この制度は驚くほど長く続きました。異端審問が正式に廃止されたのは1834年のことで、始まってから350年以上が経っていました。
16〜17世紀黄金世紀に咲いた宗教と芸術
16世紀と17世紀は、スペインの「黄金世紀」と呼ばれる時代でした。この時代、スペインは世界で最も強い国の1つでした。南アメリカに植民地を持ち、金や銀がたくさん入ってきました。芸術や文学も大いに栄えました。
この時代の宗教は、人々の生活のすべてに関わっていました。朝起きてから夜寝るまで、1年を通して、宗教行事が生活のリズムを作っていました。日曜日にはミサに行き、イースターや聖母マリアの祝日には特別な行事がありました。
面白いのは、この時代の文学作品にも宗教が深く関わっていることです。たとえば「ドン・キホーテ」という有名な小説を書いたセルバンテスも、作品の中で宗教について触れています。劇作家のカルデロン・デ・ラ・バルカは、宗教的なテーマの劇をたくさん書きました。
画家たちも、多くの宗教画を描きました。エル・グレコという画家は、天国や聖人を描いた独特な絵で有名です。ベラスケスという画家も、王様の肖像画だけでなく、宗教的な場面を描いています。
この時代、スペインからは多くの宣教師が世界中に旅立ちました。フランシスコ・ザビエルという宣教師は、日本にもやってきました。ザビエルは1549年に鹿児島に上陸し、日本でキリスト教を広めようとしました。彼はスペイン出身ではなくバスク地方の出身でしたが、スペイン帝国の支援を受けて活動していました。
宣教師たちは南アメリカでも活動しました。彼らは現地の人々にカトリックを教えましたが、同時に現地の文化を記録したり、現地の言語を学んだりもしました。ただし、この時代の宣教活動は、今から見ると問題も多くありました。時には強制的に改宗させたり、現地の宗教や文化を否定したりすることもあったからです。
聖イグナチオ・デ・ロヨラという人は、イエズス会という宣教師の組織を作りました。イエズス会は教育に力を入れ、世界中に学校を作りました。今でも、イエズス会が作った学校は多くの国に残っています。

内戦と独裁が宗教に刻んだ傷跡
18世紀と19世紀になると、ヨーロッパ全体で大きな変化が起こりました。フランス革命が起こり、「人間の権利」や「自由」という考え方が広まりました。科学が発展し、人々の考え方も変わっていきました。
スペインでもこの影響を受けました。でも変化は簡単ではありませんでした。「教会の力を弱めるべきだ」と考える人と、「伝統的な価値を守るべきだ」と考える人が対立しました。
1835年には「メンディサバルの法令」という法律ができました。これによって、教会が持っていた多くの土地や建物が国のものになりました。修道院の多くが閉鎖され、修道士や修道女たちは行く場所を失いました。
でも面白いことに、宗教は人々の生活から完全になくなったわけではありませんでした。村々では、今までどおり教会が生活の中心でした。結婚式や葬式、お祭りなど、大切な行事はすべて教会で行われました。
19世紀の後半になると、スペインではカトリック教会を支持する保守派と、教会の影響力を減らそうとする自由派が激しく対立しました。この対立は、20世紀に起こる大きな悲劇につながっていきます。
1936年から1939年まで、スペインでは内戦がありました。これは「スペイン内戦」と呼ばれ、国を二分する悲しい戦いでした。この戦いでは、宗教も大きな役割を果たしました。
共和国側には、教会の権力を減らそうとする人々がいました。一部の過激派は教会を攻撃し、多くの神父や修道女が命を落としました。教会の建物が燃やされたり、宗教的な美術品が壊されたりしました。
一方、フランシスコ・フランコ将軍が率いる反乱軍側は、カトリック教会の支持を得ました。教会は「これは信仰を守るための戦いだ」と主張しました。
内戦の後、フランコは独裁者としてスペインを支配しました。フランコ政権は、カトリック教会と強く結びついていました。学校では宗教の授業が必須になり、結婚式は教会で挙げることが法律で決められました。他の宗教を信じることは、実質的に許されませんでした。
この時代の子どもたちは、毎日学校で祈りを唱え、カトリックの教えを学びました。日曜日にミサに行かないと、先生に叱られることもありました。社会全体が、カトリックの価値観で動いていたのです。
でも興味深いことに、この強制的な宗教教育は、後に逆の効果を生むことになります。フランコが死んだ後、多くの若者が教会から離れていったのです。
モスクが再び建つ街角が語る新しい共生
1975年、フランコが亡くなりました。その後、スペインは民主主義の国に生まれ変わりました。1978年の新しい憲法では、信仰の自由が保障されました。人々は自由に宗教を選べるようになったのです。
現代のスペインは、昔と比べるとずっと多様な社会になりました。もちろん、今でも多くの人がカトリック教徒だと答えます。でも、実際に毎週教会に通う人の数は減っています。特に若い世代では、宗教をあまり大切に思わない人が増えています。
一方で、イスラム教徒の数が増えています。これは、北アフリカや他の国からの移民が増えたためです。面白いことに、スペインには再びモスクが建てられるようになりました。これは、イスラム教徒が追い出されてから何百年もぶりのことです。
2007年には、コルドバの大モスクでイスラム教徒が祈りを捧げたいと申し出て、議論になりました。結局は許可されませんでしたが、この出来事は、スペインの複雑な宗教的歴史を思い出させるものでした。
プロテスタントやユダヤ教、仏教、ヒンドゥー教など、様々な宗教を信じる人々も暮らしています。大きな町では、いろいろな宗教施設を見ることができます。
でも、カトリックの影響は今でも社会の中に残っています。たとえば、セマナ・サンタという復活祭の週には、各地で大規模な行列が行われます。街中を宗教的な像を担いだ人々が歩き、多くの人が見物に集まります。これは宗教行事であると同時に、文化的なお祭りでもあります。
クリスマスも大切な行事です。12月になると、家々には「ベレン」という、イエスの誕生場面を再現した人形が飾られます。1月6日の「東方三博士の日」には、子どもたちがプレゼントをもらいます。
興味深いのは、多くの若者が「私は宗教を信じていない」と言いながらも、こうした行事には参加することです。宗教は、単に信仰だけでなく、家族の伝統や文化的なアイデンティティの一部になっているのです。
近年では、宗教についての議論も活発です。たとえば、学校で宗教の授業を必須にするべきかどうか、宗教的なシンボルを公共の場に置いてよいかどうかなど、様々な意見があります。
2005年、スペインは同性婚を認める法律を作りました。これはカトリック教会が反対していたことでしたが、政府は「すべての人の権利を尊重する」という立場を取りました。このように、現代のスペインでは、伝統的な宗教的価値観と、現代的な人権の考え方が、時にぶつかり合うこともあります。
スペイン各地には、今も美しい大聖堂や修道院がたくさん残っています。バルセロナのサグラダ・ファミリアは、今も建設が続いている巨大な教会で、毎年何百万人もの観光客が訪れます。サンティアゴ・デ・コンポステーラには、ヨーロッパ中から巡礼者が集まってきます。これらの場所は、宗教的な意味だけでなく、芸術や歴史の宝庫として大切にされています。
時代を超えて信仰が描くスペインの軌跡
スペインの宗教の歴史を振り返ると、様々な出来事があったことがわかります。古代ローマの神々、イスラム教とキリスト教とユダヤ教が共存した時代、レコンキスタと宗教の統一、異端審問の恐怖、宣教師たちの活動、内戦と独裁、そして現代の多様性。それぞれの時代に、宗教は人々の生活に深く関わってきました。
時には、宗教は人々を結びつけ、美しい芸術や建築を生み出しました。宗教は、困っている人を助けたり、教育を広めたりする原動力にもなりました。
でも同時に、宗教の違いが争いの原因になったこともありました。自分と違う信仰を持つ人を排除したり、自分の信仰を押し付けたりすることで、多くの悲劇が起こりました。
スペインの歴史は、「違いを認め合うことの大切さ」を教えてくれます。コルドバで3つの宗教が共存していた時代があったことは、違う信仰を持つ人々が一緒に暮らすことは可能だということを示しています。一方、異端審問の時代は、不寛容がどれほど恐ろしい結果を生むかを教えてくれます。
現代のスペインは、長い歴史を経て、より開かれた社会になろうとしています。完璧ではないかもしれませんが、様々な背景を持つ人々が共に暮らす社会を目指しています。
スペインの町を歩くと、この複雑な歴史の痕跡を至る所で見ることができます。モスクだった建物の中に建てられた大聖堂、ユダヤ人街の狭い路地、宗教画が飾られた美術館。これらすべてが、スペインの豊かで複雑な宗教の歴史を語っているのです。
私たちは、スペインの歴史から多くのことを学ぶことができます。信仰は人それぞれであり、お互いの違いを尊重することが大切だということ。そして、過去の過ちから学び、よりよい未来を作っていくことの重要性です。
スペインの宗教の歴史は、単なる昔話ではありません。それは、人間がどのように信仰と向き合い、どのように共に生きていくかという、今でも続いている物語なのです。