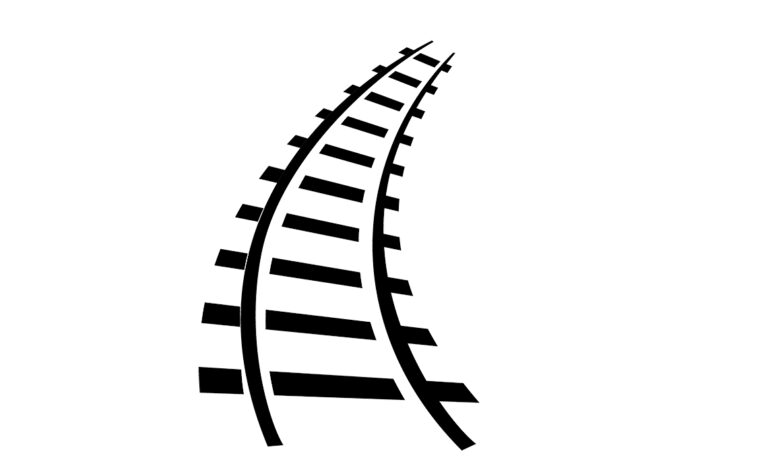Contents
世界遺産大国としての歩み
スペインは2025年現在、ユネスコ世界遺産登録数が50件を超える世界有数の遺産大国だ。
登録数は世界第3位に位置し、文化遺産の密度が極めて高い国といえる。
ローマ帝国、イスラーム王朝、キリスト教王国、そして近代国家へと変化していく中で、多様な文明がスペインの地に跡を残した。それが「遺産の多さ」につながっているのは言うまでもない。
スペインがユネスコの世界遺産条約に署名したのは1972年。フランコ政権末期の時期にあたる。当時のスペインは国際社会との距離があり、世界遺産登録への動きも遅れていた。しかし1975年の民主化以降、国際的な文化政策が活発化し、「自国の文化を世界に再評価させる」動きが一気に広がる。
1978年、最初の世界遺産登録が実現。これがのちにスペインを「遺産大国」に押し上げるきっかけとなる。1980年代から1990年代にかけて、文化省と各自治州政府が連携し、積極的な登録申請を行った。この時期に観光産業も急成長し、遺産保護と経済発展が密接に結びついていく。
最初に登録された遺産たち
最初に登録されたのは1978年の「アルタミラ洞窟」と「カセレス旧市街」などである。これらはスペインの歴史の「最初」と「中世」の両端を象徴する存在だった。
アルタミラ洞窟は、北部カンタブリア州に位置する旧石器時代の洞窟だ。1879年、地元の貴族マルセリーノ・サンツ・デ・サウトゥオラが、当時9歳の娘マリアと共に洞窟を探検しているとき、壁に描かれた野牛の絵を発見した。学会は最初、これを偽物と決めつけた。あまりにも完成度が高かったため、19世紀の人間が描いたと疑われたのだ。
だが、20世紀初頭に同様の洞窟壁画が次々と発見されると、ようやくその本物性が認められた。アルタミラは、先史時代の芸術を理解する上で世界的な転換点となった場所だ。保存のために現在は本物の洞窟を閉鎖し、精密な複製「ネオ・アルタミラ」が公開されている。これは「観光より保存を優先する」という世界遺産の理念を実践した象徴的な例でもある。
一方、カセレス旧市街はローマ時代の遺構を基礎に、中世以降の複数の文化が重なり合っている。アラブ風の塔やルネサンス様式の邸宅が同居する街並みは、スペインが「単一文化ではない国」であることを物語る。
これら2件の登録は、スペインの歴史を単なる王朝の変遷ではなく、「多文明の交差点」として世界に示す第一歩となった。

アルハンブラ宮殿とグラナダの記憶
スペインの世界遺産の中で最も象徴的な存在のひとつが「アルハンブラ宮殿」だ。
グラナダの丘にそびえるこの宮殿は、14世紀にイスラーム王朝ナスル朝の君主ムハンマド5世が築いた。壁一面に施されたアラベスク模様、光と影を計算し尽くした回廊、幾何学的に配置された噴水。宗教建築でありながら、同時に数学と哲学の結晶でもある。
しかし、この宮殿の栄光は長くは続かなかった。1492年、カトリック両王フェルナンドとイサベルによる「レコンキスタ(再征服)」が完了し、イスラーム支配は終わりを迎える。アルハンブラはキリスト教王国の象徴として扱われ、イスラーム的装飾の多くが塗りつぶされた。のちには軍事拠点や官舎として使用され、荒廃の一途をたどる。
19世紀になり、ヨーロッパのロマン主義運動の中で再評価が始まる。廃墟化した宮殿を訪れた外国人たちは、その崩れかけた美に感動した。中でもアメリカの作家ワシントン・アーヴィングが1829年に著した『アルハンブラ物語』は、宮殿の伝説を物語風に紹介し、世界中にその存在を広めた。
現在のアルハンブラの保存体制は、この再発見以降に始まったものだ。修復と再解釈の積み重ねによって、かつての敗者の建築が「スペイン文化の誇り」へと変わっていった。

サグラダ・ファミリアとガウディの思想
バルセロナの「サグラダ・ファミリア」は、近代建築の象徴として世界遺産に登録された。
設計者アントニ・ガウディは、自然を神の創造とみなし、建築をその模倣と位置づけた。彼は直線を嫌い、曲線と重力のバランスで構造を設計した。たとえば天井の柱は樹木のように枝分かれし、内部はまるで森の中のような空間になっている。
ガウディは晩年、この建築に人生の全てを捧げた。住まいも工房もすべてサグラダ・ファミリアの敷地内に移し、祈るように設計を続けた。1926年に路面電車事故で亡くなった際、完成度は全体の20%程度。設計図の多くが内戦で失われたため、後継者たちは残された資料とガウディの思想をもとに再構築を進めている。
ユネスコは2005年、この教会を「未完成であることに価値がある」として評価した。未完成という状態が、人類の創造性の継承そのものを示しているという解釈だ。現在も工事は続き、完成は2030年代と見込まれている。サグラダ・ファミリアは、過去の遺産ではなく「進行中の遺産」として、世界遺産の概念を広げる存在になった。

中世都市と保存の課題
スペインの中央部には、中世の都市構造をほぼそのまま残す街が多い。
「トレド」「アビラ」「サラマンカ」「セゴビア」などは、いずれもユネスコのリストに名を連ねる。これらの街に共通しているのは、異なる宗教と民族の共存である。
特にトレドは「三つの文化の都」と呼ばれ、キリスト教徒、ユダヤ教徒、イスラーム教徒が共存していた。狭い路地に教会とモスクとシナゴーグが隣り合う光景は、かつてのスペインが多様性を内包していたことを示している。
しかし、世界遺産登録は新たな課題も生んだ。観光客の増加により、地元住民が中心部を離れる現象が起きたのだ。観光地化が進みすぎると、街が「生きた場所」ではなく「展示物」になる。
1985年に制定された「歴史遺産法」は、この問題に対応するために作られた。文化財の保護を国家と自治体が共同で行う仕組みを整え、観光収入の一部を修復費用に充てる制度も設けた。世界遺産が単なる観光資源ではなく、地域社会の持続的な生活基盤であるという考えが定着していった。

自然遺産と環境との共存
スペインは文化遺産が圧倒的に多いが、自然遺産も重要な位置を占めている。
「ドニャーナ国立公園」はアンダルシア地方にある広大な湿地帯で、ヨーロッパとアフリカを行き来する渡り鳥の中継地だ。イベリアオオヤマネコやフラミンゴの生息地としても知られている。だが近年、観光開発や農業による水資源の枯渇が深刻化した。ユネスコは「危機遺産」の可能性を指摘し、スペイン政府に対策を求めた。これを受けて政府は灌漑農業の制限を強化し、湿地保全の方針を明確にした。
また、カナリア諸島の「テイデ国立公園」では、標高3718メートルのテイデ山がそびえる。地球上で3番目に大きい火山であり、マントル活動の研究にも貢献している。
これらの自然遺産は、スペインの「多様な地理的顔」を象徴している。雪山、砂漠、湿地、火山地帯が同じ国の中に共存しているのだ。文化遺産の背後にある自然環境を理解することも、世界遺産の本質の一部といえる。
産業遺産と近代化の記録
20世紀以降のスペインの世界遺産登録は、宗教建築から産業や技術へと広がっていった。
その代表例がバスク地方の「ビスカヤ橋」だ。1893年に完成した世界初の鉄製運搬橋で、今も現役で稼働している。橋の上を車が通るのではなく、吊り下げられたゴンドラが川を横断して人と車を運ぶ。効率的でありながら、優れたデザイン性を備えていることから、産業革命期の傑作として評価された。
また、アラゴン州の「ムデハル建築群」は、キリスト教支配下で活動していたイスラーム教徒の職人たちが築いた独自の建築様式を示す。レンガとタイルを組み合わせた幾何学的装飾は、イスラーム文化の名残を感じさせる。征服と共存の結果生まれた芸術様式として、スペインらしい歴史の混成を体現している。
政治と地域アイデンティティ
スペインの世界遺産登録の背景には、政治と地域意識の問題が常に存在する。
スペインは17の自治州を持ち、それぞれが独自の言語や文化を有している。カタルーニャ、バスク、ガリシアなどは特に強い独立志向を持ち、自らの文化遺産を「民族の誇り」として世界に示そうとしてきた。
たとえばカタルーニャではガウディ建築群が地域アイデンティティの象徴となり、バスクではビスカヤ橋が「産業の誇り」として位置づけられている。こうした動きは文化の多様性を促進する一方で、「スペインという国家全体の統一的イメージ」をどう示すかという課題も生んでいる。

世界遺産の光と影
世界遺産登録は多くの利点をもたらすが、その影響は常に一様ではない。
登録によって観光客が増え、地域経済が潤う一方で、生活コストの上昇や自然破壊、地元文化の商業化といった副作用も生じる。
特にバルセロナやセビリアでは「オーバーツーリズム(観光過多)」が問題になり、観光客の制限や宿泊税の導入などが進められている。
世界遺産が本来の目的である「保護」を超えて「消費の対象」になってしまう危険性が指摘されているのだ。
ユネスコは近年、地域社会との協働を重視する方向に方針を転換している。スペインでも、遺産を地元の教育・研究・地域振興に結びつける取り組みが広がりつつある。遺産の価値を「見る」から「使う」へ、そして「共に守る」へと変えていくことが求められている。
世界遺産が映すスペインの未来
スペインの世界遺産は、建物や景観だけでなく、そこに生きた人々の物語を内包している。
ローマの水道橋、イスラームの宮殿、ゴシックの大聖堂、近代の芸術建築。これらが同じ国の中に共存していること自体が、スペインという国の特異性を示している。
21世紀のスペインでは、気候変動、都市化、観光圧力といった新たな課題が文化遺産の存続を脅かしている。しかし、過去に何度も危機を乗り越えてきたスペインの歴史を見れば、これもまた次の再生の段階にすぎない。
ユネスコの登録リストは、単なる名誉の記録ではなく、「人類が残した課題の一覧表」としての側面も持っている。
スペインの遺産が語るのは、栄光の歴史ではなく、失敗と再生を繰り返してきた人間の営みそのものだ。守ること、見せること、使うこと。そのすべてのバランスの中で、スペインは今も「遺産大国」としての責任を果たそうとしている。