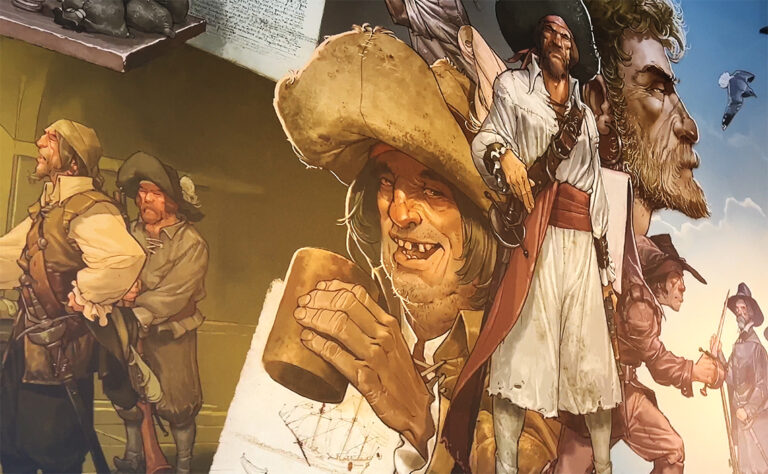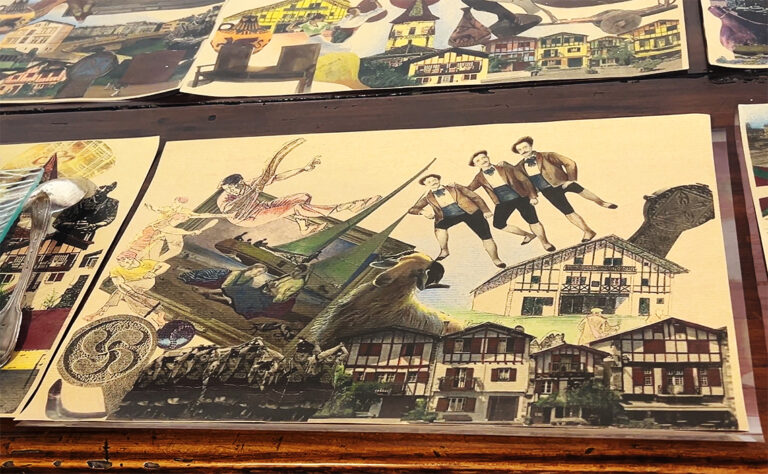序章:なぜ「サンセバスチャン=美食の街」と言われるのか
サンセバスチャンという名前を聞いたことがある人は多いだろう。
スペイン北部、バスク地方の海沿いにある人口18万人ほどの小さな町だ。
世界中のグルメ雑誌やテレビ番組で「美食の都」「食の聖地」と紹介され、特に“ピンチョス”と呼ばれる一口サイズの料理が有名である。
この町の旧市街を歩くと、バルがずらりと並んでいる。カウンターには色とりどりのピンチョスが山のように並び、観光客は皿を手に取り、グラスワインを片手に立ち食いを楽しむ。
それは確かに華やかで、旅情をかき立てる光景だ。
だが、ここでひとつ考えてみたい。
なぜ、世界の人々は「サンセバスチャンこそ美食の街」と信じるようになったのだろうか?
実はそこには、観光とメディアが作り出した“イメージの連鎖”がある。
1980年代、スペインは民主化の波の中で観光業を再生しようとしていた。
そのとき、バスク地方の料理人たちが「ヌエバ・コシーナ・バスカ(新バスク料理)」という運動を起こし、フランスのヌーベル・キュイジーヌの影響を受けて創作料理を発展させた。
地元の素材を使いながらも、洗練された盛り付けや軽やかな味付けを追求したその料理は、スペイン料理に革命をもたらした。
この運動の中心がサンセバスチャンだったため、次第に「ここがスペインの食都だ」という評判が広まっていったのだ。
さらに、1990年代になるとミシュランガイドが同地のレストランに次々と星を与え、「人口あたり三ツ星レストランの数が世界一」というキャッチコピーが生まれた。
この“数字の魔法”が、サンセバスチャンの名を世界中に轟かせたのである。
しかし、そのイメージの裏には、知られざる現実がある。

第一章:ピンチョス文化の誤解と現実
観光客がサンセバスチャンを訪れると、まず向かうのが旧市街のバル街だ。
確かにそこでは、芸術品のように美しいピンチョスが並び、インスタグラムにぴったりの光景が広がっている。
しかし実際のところ、地元の人たちは毎日あのピンチョスを食べているわけではない。
本来のピンチョスとは、もっと素朴なものだった。
パンの上にアンチョビやピクルス、卵などを刺して止めた、家庭的な軽食。
今のように華やかな創作料理が並ぶようになったのは、観光業が盛んになった2000年代以降のことだ。
つまり、現在のピンチョス文化は「観光向けに洗練されたショーケース」でもあるのだ。
たとえば、ある老舗バルの店主はこう話す。
「昔はこんなに手間をかけなかったよ。観光客が写真を撮るようになって、見た目を意識するようになったんだ」
地元の人々は、仕事帰りに一杯のチャコリ(地元の白ワイン)とシンプルなタパスをつまむ程度。
むしろ、彼らの“日常の食”は家の食卓や小さな食堂での料理にある。
このことを知らずに訪れた観光客は、「どの店も絶品」「ハズレがない」と感じるかもしれない。
しかしそれは、彼らが観光客向けに磨かれた表層の一部しか見ていないからだ。
実際に現地で長く暮らした人々に聞くと、「ピンチョスにも当たり外れはある」「店によって味は大きく違う」という声は少なくない。
“美食の街”という評判は、現実の多様さを覆い隠しているのだ。

第二章:ミシュランの魔法と数字のトリック
サンセバスチャンが「人口あたり三ツ星レストランが多い」と言われるのは事実である。
だが、その数字の裏にはカラクリがある。
まず、そもそもサンセバスチャン市の人口は18万人ほど。
ここに三ツ星レストランが3軒、二ツ星・一ツ星を含めると十数軒が存在する。
確かに人口比で計算すると高い比率になるが、絶対数としては東京の足元にも及ばない。
東京には現在、ミシュラン星付きレストランが300軒を超える。
世界で最も多い都市だ。
しかも、ここでは寿司、天ぷら、フレンチ、イタリアン、中華、和食、カレーまで、あらゆる国と地域の料理が高いレベルで共存している。
つまり、東京は「多様性の上に成り立つ美食都市」なのだ。
また、ミシュランの評価基準にも地域差がある。
ヨーロッパでは“高級レストラン文化”が基準となっており、カジュアルな店は対象外になりやすい。
一方、東京では路地裏のカウンター寿司やラーメン店までも星を得ることがある。
それは、日本人が「料理人=職人」としての技を重視する文化を持っているからだ。
さらに言えば、ミシュランの星を得たレストランの多くは観光客が予約を殺到させるため、地元の人々が普段使いする店ではなくなる。
サンセバスチャンの三ツ星店「アルサック」「アケラレ」「ムガリッツ」も、地元の人が気軽に行ける価格帯ではない。
むしろ、“美食の街”という称号が、地元の食文化を高価格化させる paradox(逆説)を生んでいるのだ。

第三章:東京こそ真の“美食の都”である理由
さて、ではなぜ「本当の美食の街」は東京だと言えるのか。
理由はひとつではない。
歴史、文化、経済、そして“食への敬意”が何層にも重なっているからだ。
まず、食材の豊かさである。
日本列島は南北に長く、四季がはっきりしている。
北海道の魚介から九州の野菜まで、異なる気候と土壌が生み出す食材が集まる。
築地(現・豊洲)市場を中心に、全国の旬が毎朝東京に届く。
つまり、東京は「全国の味覚の終着点」なのだ。
次に、料理人の層の厚さ。
東京では、職人がひとつの技を極める文化が根づいている。
寿司職人が何十年も修業する話は有名だが、ラーメンやカレーの世界でも同様だ。
「一杯の丼で勝負する」という覚悟が、東京の街角のいたるところにある。
ミシュランの星があってもなくても、味のレベルが全体的に高い。
これが、サンセバスチャンとの最大の違いである。
さらに、東京の食文化を支えているのは「混ざり合いの力」だ。
江戸時代の屋台文化、明治以降の西洋化、戦後のラーメンブーム、平成のグローバル化。
東京は常に外の文化を吸収し、それを日本人の感性で再構築してきた。
だから、フランス料理も東京では独自の“東京風フレンチ”に進化する。
スペイン料理も例外ではなく、バスク料理を学んだシェフが東京で新しい皿を生み出している。
そして何よりも、東京の“食”には日常の豊かさがある。
コンビニのおにぎり、立ち食いそば、商店街の惣菜屋。
これらのクオリティの高さは、海外の旅行者が驚くほどだ。
「日本では、安くてもうまい」という言葉が観光客の定番になっている。
サンセバスチャンのように観光のために磨かれた料理ではなく、日常生活そのものが美食文化になっている。
この差は、数字では測れない深さがある。

終章:サンセバスチャンと東京、二つの“美食”の物語
サンセバスチャンは、たしかに魅力的な町である。
海と山に囲まれた風景、親しみやすいバル文化、人々の誇り。
美食の名声は、その土地の人々が努力して築いたものであり、決して偽物ではない。
しかし、「どの店もレベルが高い」というのは誤解だ。
そこには観光業が作り出した演出も多く、実際には当たり外れがある。
本当のサンセバスチャンの美食は、観光客のカメラの外側、家庭や地元の食堂にこそ息づいている。
一方で、東京の“美食”は観光ではなく、日常の中で自然に育った文化である。
庶民の味と高級料理が共存し、どちらも真剣に「おいしさ」を追求している。
料理人も食べる側も、味に対して誠実だ。
それが世界中のシェフたちを惹きつけ、「東京で修業したい」と言わせる理由である。
もし「美食の街」という言葉を、
“料理がうまい店が集まる場所”ではなく、
“おいしいものを大切にする人々が暮らす街”と定義するなら、
その答えは明らかだ。
サンセバスチャンは「美食を観光化した街」。
東京は「日常が美食を生み出す街」。
どちらが上という話ではない。
しかし、“すべての店がうまい”という幻想を超えたときにこそ、
本当の「美食の意味」が見えてくるのではないだろうか。